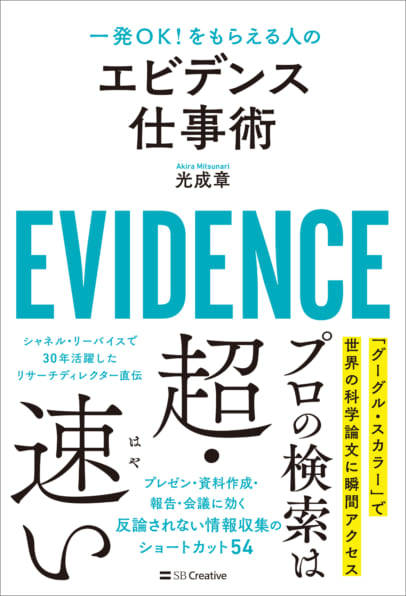カルチャー
2017年5月9日
野村克也が憂う、WBC後遺症――開幕から不調の代表選手たち
WBCで活躍しても、ペナントレースで活躍できなかったらどうなるか
WBCの代表に選ばれることはすなわち、所属チームに帰ればチームの中心を担う立場の選手たちばかりである。シーズン終了後に翌年の契約を交わすのは、いうまでもなく選手たちが所属する球団であり、年俸は、4年に1回開催されるWBCの成績ではなく、ペナントレースでどれだけ貢献してくれたかで決定される。
たとえば投手であれば勝利数や防御率などの目に見えて分かる成績はもとより、優勝争いをしていれば天王山と呼ばれる、シーズンの行方を左右するような試合で、どれだけ貢献してくれたかもフロントは査定の際に重要視していると聞く。
もちろんこのことは投手だけに限らず野手も同様だ。打撃だけでなく、守備面での成績だって査定の対象になる。そうしたときに、「WBCよりシーズンのほうが大事」と考える選手だって出てきても、おかしな話ではない。
たとえば今回の大会で、打撃面で飛躍的に成長したと思われた巨人の小林誠司は、ペナントレースが始まった途端、大ブレーキとなった。打席に立てば凡打の山では、「WBCのときの打撃はいったい何だったのだろう?」とあまりの不振ぶりに不思議に思う野球ファンだっているに違いない。
「キャッチャーは現場における第二の監督である」という持論がある野村氏にしてみれば、精神的な負担も相当あるかもしれないが、このままだと昨季よりも低い打率となってしまう可能性だってある。
そうなると、せっかくWBCで活躍しても、いざペナントレースで大不振に陥ってしまったりしたら、シーズンオフの契約更改でなんらかの影響を及ぼしてしまうかもしれない。
実際に野村氏は『負けを生かす極意』のなかで、こう指摘している。
「WBCと、契約に大いに関係してくるシーズンの成績を天秤にかけたら『シーズンで活躍するほうが大切』だと考えている選手だっているかもしれない。そうしたときに、なんらかの理由をつけて『WBCは辞退します』と言う選手は今後も出てくるだろう」
今一度、WBCの臨み方について、プロ野球関係者は大いに議論すべき
それではWBCを辞退した選手たちを非難できるかどうか? 答えはノーである。 野村氏は自らがチームを預かる監督としての立場だったとして、同著のなかで次のように持論を述べている。
「私が所属チームの指揮官であれば、『頑張ってこい』と送り出す一方で、『ケガだけはするなよ』という親心も働いてしまうものだ。ましてや開幕を控えたこの時期に、主力選手を送り出すことの不安は、どのチームの指揮官も内心抱えているだろうが、それを表に出してしまうと世間から非難を浴びてしまう」
野村氏が楽天の監督だった2009年の第2回WBCでは、岩隈久志と田中将大が選ばれ、日本の大会2連覇に貢献した。2人とも今やメジャーで活躍する投手だが、当時の楽天でも先発を担う大事な柱であった。野村氏の心情を吐露したこの言葉は、まさに本音そのものといえよう。
そうなると「WBCの代表メンバーに選ばれ、出場すること」がどれほど名誉だと選手自身が感じてくれるか、ということに尽きる。その場合、各チームの主軸を担う選手にこだわる必要がないという考えだってあるだろう。
だが、野村氏は侍ジャパンのメンバー選出について、次のように持論を述べている。
「『出たい選手だけが出ればいい』という姿勢では、誰もが納得するようなメンバー選出ができるとは思えないし、大谷のWBC辞退に始まる諸問題は、次の大会前までにクリアすべき事案となったに違いない」
日本の代表選手の選考について、所属チームとの契約上の問題でメジャーリーガーが難しいのであれば、少なくとも日本のトッププレイヤーであることが望ましいと、野村氏は考えている。そのためには、メンバーの人選の基準について、NPB(日本野球機構)やプロ野球選手会などは、現場の意見を反映させるべく、もっと積極的に議論を交わしておくべきだろうというのが、同氏の主張するところだ。
このほかにも同著では、外野手出身監督では常勝チームを作れない理由や、今のプロ野球を見て現有戦力で足りないもの、監督通算成績「1565勝、1563敗、76分」の筆者が伝えたい敗北学、「負け」を次に生かせるリーダーの条件などについても述べている。
(了)
野村 克也(のむら かつや)
1935年生まれ。京都府立峰山高校を卒業し、1954年にテスト生として南海ホークスに入団。3年目の1956年からレギュラーに定着すると、現役27年間にわたり球界を代表する捕手として活躍。歴代2位の通算657本塁打、戦後初の三冠王などその強打で数々の記録を打ち立て、 不動の正捕手として南海の黄金時代を支えた。「ささやき戦術」や投手のクイックモーションの導入など、駆け引きに優れ工夫を欠かさない野球スタイルは現在まで語り継がれる。また、70年の南海でのプレイングマネージャー就任以降、延べ四球団で監督を歴任。 他球団で挫折した選手を見事に立ち直らせ、チームの中心選手に育て上げる手腕は、「野村再生工場」と呼ばれ、 ヤクルトでは「ID野球」で黄金期を築き、楽天では球団初のクライマックスシリーズ出場を果たすなど輝かしい功績を残した。 インタビュー等でみせる独特の発言はボヤキ節と呼ばれ、 その言葉はノムラ語録として多くの書籍等で野球ファン以外にも広く親しまれている。 スーパースターであった王・長嶋と比較して、自らを「月見草」に例えた言葉は有名である。現在は野球解説者としても活躍。著書に『名将の条件』(SB新書)など多数ある。
1935年生まれ。京都府立峰山高校を卒業し、1954年にテスト生として南海ホークスに入団。3年目の1956年からレギュラーに定着すると、現役27年間にわたり球界を代表する捕手として活躍。歴代2位の通算657本塁打、戦後初の三冠王などその強打で数々の記録を打ち立て、 不動の正捕手として南海の黄金時代を支えた。「ささやき戦術」や投手のクイックモーションの導入など、駆け引きに優れ工夫を欠かさない野球スタイルは現在まで語り継がれる。また、70年の南海でのプレイングマネージャー就任以降、延べ四球団で監督を歴任。 他球団で挫折した選手を見事に立ち直らせ、チームの中心選手に育て上げる手腕は、「野村再生工場」と呼ばれ、 ヤクルトでは「ID野球」で黄金期を築き、楽天では球団初のクライマックスシリーズ出場を果たすなど輝かしい功績を残した。 インタビュー等でみせる独特の発言はボヤキ節と呼ばれ、 その言葉はノムラ語録として多くの書籍等で野球ファン以外にも広く親しまれている。 スーパースターであった王・長嶋と比較して、自らを「月見草」に例えた言葉は有名である。現在は野球解説者としても活躍。著書に『名将の条件』(SB新書)など多数ある。