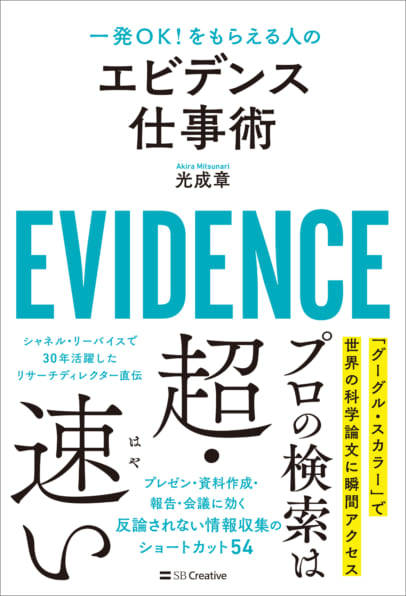ビジネス
2017年5月24日
野村克也氏がボヤく、「褒める上司」は信用できない
「部下を褒めてばかりいる上司」は問題だ
さらに野村氏は、上司が部下に対して「褒めること」を良しとする指導に警鐘を鳴らしている。
「最近は部下に媚びて機嫌を窺うような上司もいるのだという。こんなことをして、本当に部下のためになるだろうか。そう疑問に思ってしまうのだが、私だったら部下に媚びるようなマネは絶対にしない。ではなぜこのような態度をとってしまうのか。それは上司が自分の指導に対して理論や自信を持っていないからだ」
組織を指揮していく人間であれば、「私はこうしていきたい」と明確に自分の指針を提示して、しかるべき方向にみんなを導いていかなければならない。ところが、それがないのは、「これだけは絶対に譲れない」という、自分なりの考えを持っていないことの裏返しであると、野村氏は話す。
そして、部下に媚びてばかりの人がリーダーになると、次のような弊害が起きると予測している。
「部下から出てきたさまざまな意見に対して、みんなを立てようとするあまり、何一つ決められないということだってあり得る。『あの人はいい人だ』と言われている人ほど、結局のところ、相手に本音を話していないとも言い換えられる。発言した人の気分を損なわないような言い方をしているから、『いい人』でいられるのであり、『これだけは絶対に譲れない』という信念が欠けているからこそ、信用するに値しない人物なのだと、私はそうとらえてしまう」
だからこそ、野村氏は部下に対して私の野球哲学を明確に提示し、部下の顔色を窺うことなど、一度たりともしていなかった。
リーダーは部下に対していい人になる必要もなければ、顔色を気にしておべんちゃらを使う必要など一切ない。「私はこういう方針でやっていく」という明確な哲学を部下に提示することが必要だというのを、世のリーダーたちは知っておくべきだと、野村氏は力説している。
技術的限界にぶつかったとき、創意工夫ことが大切だ
野村氏は、人が成長していくのには、段階があり、「もうここでいいや」と自分で諦めてしまった時点で、それ以降の成長は望めないと話す。では、壁にぶつかったときにどう乗り越えていくべきなのだろうか。野村氏は、ドラフトを経て、プロに入団してくる選手たちを例に、次のように語っている。
「いざプロ入りすると、先輩たちのすごさに圧倒されてしまうケースがほとんどだ。高校時代に通算40本のホームランを打っていたとしても、相手の投手のレベルが低かったり、MAX150キロの真っすぐを投げるといっても、制球が今一つで捕手の構えたところに投げられないなど、なにかしらの課題を抱えているのも、新人選手によく見られることである。
そこで先輩選手に交じって練習すると、スイングスピードが違っていたり、制球が抜群に良かったりするものだから、そこで自分の実力と比較する。『オレの来るような世界じゃなかった』と絶望感に打ちひしがれるのも、ある意味、仕方のないことかもしれない。
だが、本当の勝負はそこからだ。プロのレベルの高さを身に沁みて痛感したときに自分はどういう選手になるべきか。自分では長距離打者だと思っていたのに、プロに入ったらそうなれそうもないと悟ったら、どういうプレーヤーを目指すべきか。あるいは制球に苦しんでいたら、現状をどう打破していけばいいのか。そこから己との格闘が始まる。
人間には技術的限界があるが、挑戦することには限界がない。どんな人間にも技術的な限界はいつかやってくる。たとえ1年目に好成績を残しても、2年目には相手から研究し尽くされ、1年目と同じような成績を残せない。俗にいう『2年目のジンクス』は、相手の執拗なまでの研究と、己の慢心が招いた結果だと分析しているが、持って生まれたセンスだけで通用するほどプロの世界は甘くない。
そのことを理解していれば、たとえ技術的な限界にぶつかっても、『このままじゃいけない』という危機意識と飽くなき探求心が芽生えてくるものだ。
昔も今も、プロ野球の第一線で活躍している選手は、皆技術的な壁にぶつかってそれを乗り越えてきた。そのために必要なのは、頭を使って創意工夫を積み重ねていく重要性に気づくことだ」
技術の限界にぶつかったときには、「もうダメだ」と諦めるのではなく、「ここからどうやったら壁を乗り越えられるか」を考えることで、現状を打開することができるということを、指導者は理解し、部下の指導にあたるべきだ、というのが、野村氏の主張するところだ。みなさんもぜひ、野村氏の言葉をヒントに部下の育成にあたってほしい。
(了)
野村 克也(のむら かつや)
1935年生まれ。京都府立峰山高校を卒業し、1954年にテスト生として南海ホークスに入団。3年目の1956年からレギュラーに定着すると、現役27年間にわたり球界を代表する捕手として活躍。歴代2位の通算657本塁打、戦後初の三冠王などその強打で数々の記録を打ち立て、 不動の正捕手として南海の黄金時代を支えた。「ささやき戦術」や投手のクイックモーションの導入など、駆け引きに優れ工夫を欠かさない野球スタイルは現在まで語り継がれる。また、70年の南海でのプレイングマネージャー就任以降、延べ四球団で監督を歴任。 他球団で挫折した選手を見事に立ち直らせ、チームの中心選手に育て上げる手腕は、「野村再生工場」と呼ばれ、 ヤクルトでは「ID野球」で黄金期を築き、楽天では球団初のクライマックスシリーズ出場を果たすなど輝かしい功績を残した。 インタビュー等でみせる独特の発言はボヤキ節と呼ばれ、 その言葉はノムラ語録として多くの書籍等で野球ファン以外にも広く親しまれている。 スーパースターであった王・長嶋と比較して、自らを「月見草」に例えた言葉は有名である。現在は野球解説者としても活躍。著書に『名将の条件』(SB新書)など多数ある。
1935年生まれ。京都府立峰山高校を卒業し、1954年にテスト生として南海ホークスに入団。3年目の1956年からレギュラーに定着すると、現役27年間にわたり球界を代表する捕手として活躍。歴代2位の通算657本塁打、戦後初の三冠王などその強打で数々の記録を打ち立て、 不動の正捕手として南海の黄金時代を支えた。「ささやき戦術」や投手のクイックモーションの導入など、駆け引きに優れ工夫を欠かさない野球スタイルは現在まで語り継がれる。また、70年の南海でのプレイングマネージャー就任以降、延べ四球団で監督を歴任。 他球団で挫折した選手を見事に立ち直らせ、チームの中心選手に育て上げる手腕は、「野村再生工場」と呼ばれ、 ヤクルトでは「ID野球」で黄金期を築き、楽天では球団初のクライマックスシリーズ出場を果たすなど輝かしい功績を残した。 インタビュー等でみせる独特の発言はボヤキ節と呼ばれ、 その言葉はノムラ語録として多くの書籍等で野球ファン以外にも広く親しまれている。 スーパースターであった王・長嶋と比較して、自らを「月見草」に例えた言葉は有名である。現在は野球解説者としても活躍。著書に『名将の条件』(SB新書)など多数ある。