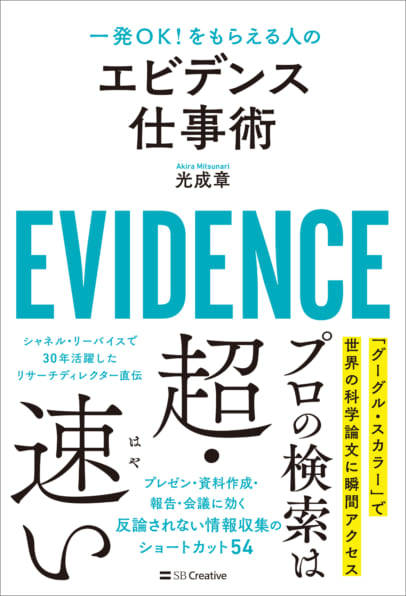カルチャー
2015年11月19日
市場の拡大は「共同体」を消滅させる
[連載]
宗教消滅─資本主義は宗教と心中する─【12】
文・島田裕巳
水野和夫が指摘した利子率低下の意味
ベストセラーになった水野和夫の著作『資本主義の終焉と歴史の危機』(集英社新書)のなかで、経済成長の指標として利子率が注目されているが、それぞれの国で経済発展が限界に達すると、利子率の低下という事態が起こる。
水野の議論が注目されたのは、現代において利子率の低下が著しい国として日本があげられていた点である。日本では、1997年に10年国債の利回りが2.0パーセントを下回り、その後ずっとその事態が続いている。
その後、アメリカやイギリス、ドイツでも、10年国債が2.0パーセントを下回るようになり、その点では日本が先鞭をつけた形になった。日本は、1990年代後半にバブル経済が起こり、それが最初に崩壊した国でもある。高度経済成長と呼ばれた戦後の驚異的な発展によって、日本は他の先進国を追い越してしまったのである。
利子率が低下するということは、資本を投下しても、十分な利潤を得られなくなるということであり、それは、資本の自己増殖が不可能になったことを意味する。水野は、利子率の低下は、「資本主義が資本主義として機能していないという兆候」であるとしている。
日本に先駆けて、利子率の極端な低下を経験したところがあった。それが、17世紀初頭のイタリア・ジェノヴァで、金利が2パーセントを下回る時代を11年にわたって経験している。
当時、スペインの皇帝が南米で銀を掘り出し、スペインの取引先であるイタリアの銀行にそれが集まってきたため、イタリアでは、マネーがだぶつくという事態が起こった。金銀はあっても、その投資先がないという状況に陥ったのである。
すでに16世紀のイタリアでは、山の上までブドウ畑が広がるという事態が生まれていた。それはワインを製造するためで、当時はワイン製造が最先端の産業だった。頂上までブドウ畑が広がれば、その先はない。だから、イタリアでは投資先がなくなってしまったのである。
水野は、現代において利潤率の低下という事態が起こったのは1974年頃のことではないかと言い、その原因として、73年と79年に起こったオイル・ショックと、75年のベトナム戦争終結をあげている。
国内にフロンティアを失ったアメリカは、海外にそれを求めるようになったわけだが、ベトナム戦争で敗れたことによって、それもまた不可能になった。
一方、オイル・ショックは、石油の生産国が力をつけることによって、先進国がエネルギーを安く買いたたくことができなくなったことを意味する。資源が高騰すれば、生産コストはかさみ、それは利潤率の低下に結びついていく。
それ以降のアメリカは、IT技術と金融とを結びつけることによって、「電子・金融空間」を拡大していくことに活路を見いだしていくことになる。
しかしそれは、金融商品に手を出すことができる富裕層と、それができない貧困層の格差を拡大するとともに、バブルとその崩壊がくり返される状況を生んだ。アフリカや宇宙といったことが、これからの市場として期待されていると宣伝されるのも、いよいよグローバル化も行き着くところまで行ってしまい、市場を拡大する空間を見出せなくなっているからである。
日本の高度成長と行きつく先
日本では、中世以降、貨幣経済が浸透し、近世に入ると、大坂(現在の大阪)などを中心に金融経済も発展を見せていく。人口も近世がはじまる時代から近代に突入する時点では3倍程度に拡大していた。それが、明治に入っての急速な近代化の基礎にもなっていくが、西欧の産業革命にふれるまで、日本の社会には、農業を拡充していく以外には、経済を発展させていく手段がなかった。
海外との貿易によって経済が発展していくことは、南蛮貿易の時代に証明されたが、江戸時代の日本は鎖国政策をとり、積極的に貿易を拡大していこうとはしなかった。経済発展が国家の目標になるのは明治になってからで、政府は「富国強兵」のスローガンを掲げて、急速な工業化による経済発展をめざした。
近代的な軍事力をもっていなかった日本が、明治維新からわずか30年で日清戦争を戦い、それに勝利したことはその点で驚異的なことである。当時の日本は、軍事力を拡大することで、中国大陸における権益を拡大し、それによる市場の拡大をめざした。大陸は、当時の日本にとってフロンティアにほかならなかった。
しかし、その結果、日本はロシアとの戦争には勝利をおさめたものの、最終的にはアメリカとの戦争に敗れ、市場拡大の活路を中国大陸に求めることができなくなる。
戦後においては、植民地主義による経済発展の道を封じられたものの、国内の市場はまだ開拓されておらず、日本は新しい日本国憲法のもと、産業構造の大規模な転換によって、国内需要を高めることに成功する。それが、高度経済成長に結びつくわけで、それはアメリカの場合と同様に、1970年代に入るまで続く。
このときに重要なことは、経済発展によって地方から都市への大規模な人口移動が起こるなか、近代化を阻んでいるものとして、地方の村落共同体が槍玉にあげられたことである。
日本は家社会であり、それが、個人の自立を妨げ、近代的自我の発展を阻害していることが指摘された。真に自立した個人を創造し、社会全体の近代化をはかるためには、村落共同体も家社会も解体していかなければならないというわけである。
一方では、人口移動によって地方の過疎化が起こり、それが問題になることで、各種の対策がたてられた。しかし、現実には、村落共同体の解体は進行し、それが日本における宗教の消滅という事態に結びついていくのである。
(続)
[連載]宗教消滅─資本主義は宗教と心中する─ 記事一覧
[1]資本主義は宗教と心中する―迫り来る『宗教消滅』の時代―
[2]宗教と政治経済の関係を説明する一つのセオリー
[3]フランスの「カトリック消滅」
[4]ドイツ、教会離れの原因は「教会税」にあり
[5]ヨーロッパを覆う「イスラム化」という恐怖
[6]韓国の宗教――戦後、キリスト教の驚異的な成長
[7]中国で起きる、宗教がらみの社会問題
[8]ローマ法王、アメリカ訪問は何を意味するか ―アメリカ・南米、カトリックの危機
[9] 世界の宗教は「世俗化」に向かっている【第二部】
[10]キリスト教は資本主義と親和的なのか
[11]近代経済学に影響を与える「ユダヤ・キリスト教」の信仰
[12]市場の拡大は「共同体」を消滅させる
[13]日本にキリスト教を伝えた「ポルトガル」の経済的窮状
[14]止まらない日本の新宗教の衰退
[15]「統一教会」「幸福の科学」で進む信者の高齢化
[16]創価学会でさえ退潮の兆しが見えている
[1]資本主義は宗教と心中する―迫り来る『宗教消滅』の時代―
[2]宗教と政治経済の関係を説明する一つのセオリー
[3]フランスの「カトリック消滅」
[4]ドイツ、教会離れの原因は「教会税」にあり
[5]ヨーロッパを覆う「イスラム化」という恐怖
[6]韓国の宗教――戦後、キリスト教の驚異的な成長
[7]中国で起きる、宗教がらみの社会問題
[8]ローマ法王、アメリカ訪問は何を意味するか ―アメリカ・南米、カトリックの危機
[9] 世界の宗教は「世俗化」に向かっている【第二部】
[10]キリスト教は資本主義と親和的なのか
[11]近代経済学に影響を与える「ユダヤ・キリスト教」の信仰
[12]市場の拡大は「共同体」を消滅させる
[13]日本にキリスト教を伝えた「ポルトガル」の経済的窮状
[14]止まらない日本の新宗教の衰退
[15]「統一教会」「幸福の科学」で進む信者の高齢化
[16]創価学会でさえ退潮の兆しが見えている
【著者】島田 裕巳(しまだ ひろみ)
現在は作家、宗教学者、東京女子大学非常勤講師、NPO法人葬送の自由をすすめる会会長。学生時代に宗教学者の柳川啓一に師事し、とくに通過儀礼(イニシエーション)の観点から宗教現象を分析することに関心をもつ。大学在学中にヤマギシ会の運動に参加し、大学院に進学した後も、緑のふるさと運動にかかわる。大学院では、コミューン運動の研究を行い、医療と宗教との関係についても関心をもつ。日本女子大学では宗教学を教える。 1953年東京生まれ。東京大学文学部宗教学宗教史学専修課程卒業、東京大学大学院人文科学研究課博士課程修了。放送教育開発センター助教授、日本女子大学教授、東京大学先端科学技術研究センター特任研究員を歴任。主な著書に、『創価学会』(新潮新書)、『日本の10大新宗教』、『葬式は、要らない』、『浄土真宗はなぜ日本でいちばん多いのか』(幻冬舎新書)などがある。とくに、『葬式は、要らない』は30万部のベストセラーになる。生まれ順による相性について解説した『相性が悪い!』(新潮新書)や『プア充』(早川書房)、『0葬』(集英社)などは、大きな話題になるとともに、タイトルがそのまま流行語になった。
現在は作家、宗教学者、東京女子大学非常勤講師、NPO法人葬送の自由をすすめる会会長。学生時代に宗教学者の柳川啓一に師事し、とくに通過儀礼(イニシエーション)の観点から宗教現象を分析することに関心をもつ。大学在学中にヤマギシ会の運動に参加し、大学院に進学した後も、緑のふるさと運動にかかわる。大学院では、コミューン運動の研究を行い、医療と宗教との関係についても関心をもつ。日本女子大学では宗教学を教える。 1953年東京生まれ。東京大学文学部宗教学宗教史学専修課程卒業、東京大学大学院人文科学研究課博士課程修了。放送教育開発センター助教授、日本女子大学教授、東京大学先端科学技術研究センター特任研究員を歴任。主な著書に、『創価学会』(新潮新書)、『日本の10大新宗教』、『葬式は、要らない』、『浄土真宗はなぜ日本でいちばん多いのか』(幻冬舎新書)などがある。とくに、『葬式は、要らない』は30万部のベストセラーになる。生まれ順による相性について解説した『相性が悪い!』(新潮新書)や『プア充』(早川書房)、『0葬』(集英社)などは、大きな話題になるとともに、タイトルがそのまま流行語になった。