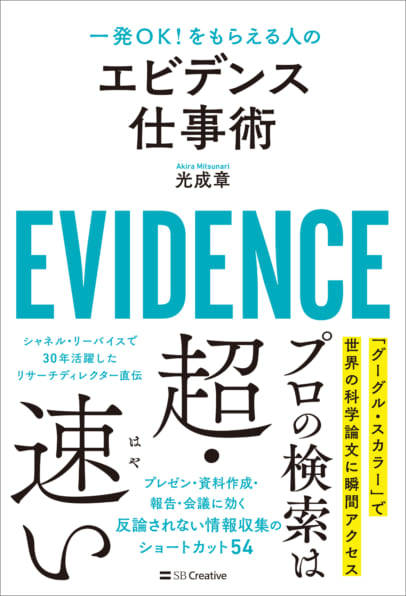カルチャー
2015年11月5日
キリスト教は資本主義と親和的なのか
[連載]
宗教消滅─資本主義は宗教と心中する─【10】
文・島田裕巳
キリスト教の信仰と経済の関係
では、キリスト教世界の場合に、信仰と経済との関係はどのようになるのだろうか。キリスト教の信仰は果たして資本主義と親和的なものなのだろうか。それを問わなければならない。
まずその際に押さえておかなければならないのは、イスラム教とキリスト教との性格の違いである。
イスラム教の場合、宗教の世界と世俗の世界は一体であり、両者は分離されていない。俗にまみれた現実の世界と、神聖な信仰の世界は区別されない。したがって、イスラム教の聖職者は皆俗人である。
それに対して、キリスト教の場合には、(ここでは基本的にカトリックにおいてということになるが)宗教の世界と世俗の世界とは厳格に区別され、両者は分離されている。俗にまみれた現実の世界と、神聖な信仰の世界は区別されており、聖職者は、世俗の世界を捨てなければならない。キリスト教の聖職者は、誰もが生涯独身を誓い、神に仕える人間ばかりである。
この違いは、二つの宗教の世界観にも影響を与える。イスラム教では、商売による金儲けはそのまま正当な行為として認められるが、キリスト教ではそうではない。キリスト教でむしろ強調されるのは、「禁欲」ということである。
キリスト教の聖職者は、禁欲を貫かなければならず、性的な欲望を満たそうとしてはならないと定められるとともに、労働に勤しむことも基本的は禁じられている。修道会のなかには、労働を高く評価し、それを実践に取り込んでいるところもあるが、神父などは基本的に宗教行為に専念し、ほかに仕事をもたない。
ただし、プロテスタントの場合には、そうした世俗の世界から離れた聖職者というものは存在しない。牧師は皆俗人であり、結婚し、家庭生活を営んでいる。
アダムとエバまで遡る「原罪」の意識
では、プロテスタントの場合には、カトリックにおいて禁欲が重視されているのと違い、禁欲的な傾向は見られないのだろうか。その点で、イスラム教と変わらないのだろうか。
実はそうではない。プロテスタントの世界では、「禁欲」は信者全員が追求すべきこととされ、むしろ、それが奨励されている。
それは、キリスト教の信仰において、「原罪」の観念が存在するからである。それは、旧約聖書の「創世記」に記されたエデンの園におけるアダムとエバの物語に遡る。神は、2人にエデンの園に生えているもののなかで、善悪を知る木の実だけは食べてならないと命じていたが、蛇に誘惑されたエバは、その禁を破ってしまい、アダムにもそれを食べるよう誘った。これが原因で、2人は楽園であったエデンの園を追われる。そして、生きていくための糧を得るために労働することと、死を運命づけられたのだった。
「創世記」に記されたことは、神話的な物語であり、そこでは2人の行為が原罪とされているわけではない。しかし、木の実を食べたアダムとエバが、裸でいることに恥ずかしさを感じるようになったとされていることから、やがて2人は性の快楽を知ったと解釈され、蛇がサタンであると考えられるようになる。こうして、原罪の観念が生み出されていく。この原罪の観念は、ユダヤ教にもないし、イスラム教にも受け継がれなかった。
キリスト教の聖職者が生涯独身を守ることを求められるのも、こうした原罪の観念があるからで、それを免れるためには禁欲を貫くことが不可欠とされた。それは、俗人にも求められるようになり、子どもを作るために生殖活動を行うことは認められても、性的な快楽の追求は神の教えに背くことととらえられるようになる。
マックス・ヴェーバーが注目した「天職」の考え
ドイツの社会学者であるマックス・ヴェーバーが、聖職者に求められる禁欲を「世俗外的禁欲」ととらえ、俗人に求められる禁欲を「世俗内的禁欲」ととらえて、そこから資本主義の精神の誕生してくる過程を追っていったのが、『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』という書物である。
ヴェーバーがとくに注目したのが、カルヴィニスムである。プロテスタントは、宗教改革を経て生み出されてきたものだが、カルヴィニズムは、フランスで生まれ、スイスのジュネーブで活動したジョン・カルヴァンに遡る。カルヴァンは、神の絶対性を強調する教えを確立していった。
ヴェーバーが、カルヴィニズムに着目したのは、16世紀から17世紀にかけて、資本主義がもっとも発達したオランダ、イギリス、フランスにおいて、カルヴィニズムが広まっていたからである。
カルヴィニズムは、神の絶対性を強調することで、「予定説」という考え方を生み出していく。予定説においては、現実の世界をはるかに超越している神は、最後の審判が訪れたときに救済される人間をあらかじめ定めているとされる。ただし、人間の側は、自分がそこに含まれるかどうかを教えられていないのである。
その個人が救われるかどうかがすでに決められているのなら、いくら善行を積んでも、それは意味をなさない。逆に、悪をなしても変わらないことになる。
そうした矛盾を回避する考え方としてヴェーバーが持ち出してきたのが、もう一人の宗教改革家、マルティン・ルターが唱えた「天職」の考え方である。天職には、神から与えられた使命という意味がこめられている。ヴェーバーは、プロテスタントが優勢な民族のあいだにはこの「天職」にあたることばが存在するが、それ以外の、カトリックが優勢な地域などでは、そうした言葉を見いだすことができないとする。
[連載]宗教消滅─資本主義は宗教と心中する─ 記事一覧
[1]資本主義は宗教と心中する―迫り来る『宗教消滅』の時代―
[2]宗教と政治経済の関係を説明する一つのセオリー
[3]フランスの「カトリック消滅」
[4]ドイツ、教会離れの原因は「教会税」にあり
[5]ヨーロッパを覆う「イスラム化」という恐怖
[6]韓国の宗教――戦後、キリスト教の驚異的な成長
[7]中国で起きる、宗教がらみの社会問題
[8]ローマ法王、アメリカ訪問は何を意味するか ―アメリカ・南米、カトリックの危機
[9] 世界の宗教は「世俗化」に向かっている【第二部】
[10]キリスト教は資本主義と親和的なのか
[11]近代経済学に影響を与える「ユダヤ・キリスト教」の信仰
[12]市場の拡大は「共同体」を消滅させる
[13]日本にキリスト教を伝えた「ポルトガル」の経済的窮状
[14]止まらない日本の新宗教の衰退
[15]「統一教会」「幸福の科学」で進む信者の高齢化
[16]創価学会でさえ退潮の兆しが見えている
[1]資本主義は宗教と心中する―迫り来る『宗教消滅』の時代―
[2]宗教と政治経済の関係を説明する一つのセオリー
[3]フランスの「カトリック消滅」
[4]ドイツ、教会離れの原因は「教会税」にあり
[5]ヨーロッパを覆う「イスラム化」という恐怖
[6]韓国の宗教――戦後、キリスト教の驚異的な成長
[7]中国で起きる、宗教がらみの社会問題
[8]ローマ法王、アメリカ訪問は何を意味するか ―アメリカ・南米、カトリックの危機
[9] 世界の宗教は「世俗化」に向かっている【第二部】
[10]キリスト教は資本主義と親和的なのか
[11]近代経済学に影響を与える「ユダヤ・キリスト教」の信仰
[12]市場の拡大は「共同体」を消滅させる
[13]日本にキリスト教を伝えた「ポルトガル」の経済的窮状
[14]止まらない日本の新宗教の衰退
[15]「統一教会」「幸福の科学」で進む信者の高齢化
[16]創価学会でさえ退潮の兆しが見えている
【著者】島田 裕巳(しまだ ひろみ)
現在は作家、宗教学者、東京女子大学非常勤講師、NPO法人葬送の自由をすすめる会会長。学生時代に宗教学者の柳川啓一に師事し、とくに通過儀礼(イニシエーション)の観点から宗教現象を分析することに関心をもつ。大学在学中にヤマギシ会の運動に参加し、大学院に進学した後も、緑のふるさと運動にかかわる。大学院では、コミューン運動の研究を行い、医療と宗教との関係についても関心をもつ。日本女子大学では宗教学を教える。 1953年東京生まれ。東京大学文学部宗教学宗教史学専修課程卒業、東京大学大学院人文科学研究課博士課程修了。放送教育開発センター助教授、日本女子大学教授、東京大学先端科学技術研究センター特任研究員を歴任。主な著書に、『創価学会』(新潮新書)、『日本の10大新宗教』、『葬式は、要らない』、『浄土真宗はなぜ日本でいちばん多いのか』(幻冬舎新書)などがある。とくに、『葬式は、要らない』は30万部のベストセラーになる。生まれ順による相性について解説した『相性が悪い!』(新潮新書)や『プア充』(早川書房)、『0葬』(集英社)などは、大きな話題になるとともに、タイトルがそのまま流行語になった。
現在は作家、宗教学者、東京女子大学非常勤講師、NPO法人葬送の自由をすすめる会会長。学生時代に宗教学者の柳川啓一に師事し、とくに通過儀礼(イニシエーション)の観点から宗教現象を分析することに関心をもつ。大学在学中にヤマギシ会の運動に参加し、大学院に進学した後も、緑のふるさと運動にかかわる。大学院では、コミューン運動の研究を行い、医療と宗教との関係についても関心をもつ。日本女子大学では宗教学を教える。 1953年東京生まれ。東京大学文学部宗教学宗教史学専修課程卒業、東京大学大学院人文科学研究課博士課程修了。放送教育開発センター助教授、日本女子大学教授、東京大学先端科学技術研究センター特任研究員を歴任。主な著書に、『創価学会』(新潮新書)、『日本の10大新宗教』、『葬式は、要らない』、『浄土真宗はなぜ日本でいちばん多いのか』(幻冬舎新書)などがある。とくに、『葬式は、要らない』は30万部のベストセラーになる。生まれ順による相性について解説した『相性が悪い!』(新潮新書)や『プア充』(早川書房)、『0葬』(集英社)などは、大きな話題になるとともに、タイトルがそのまま流行語になった。